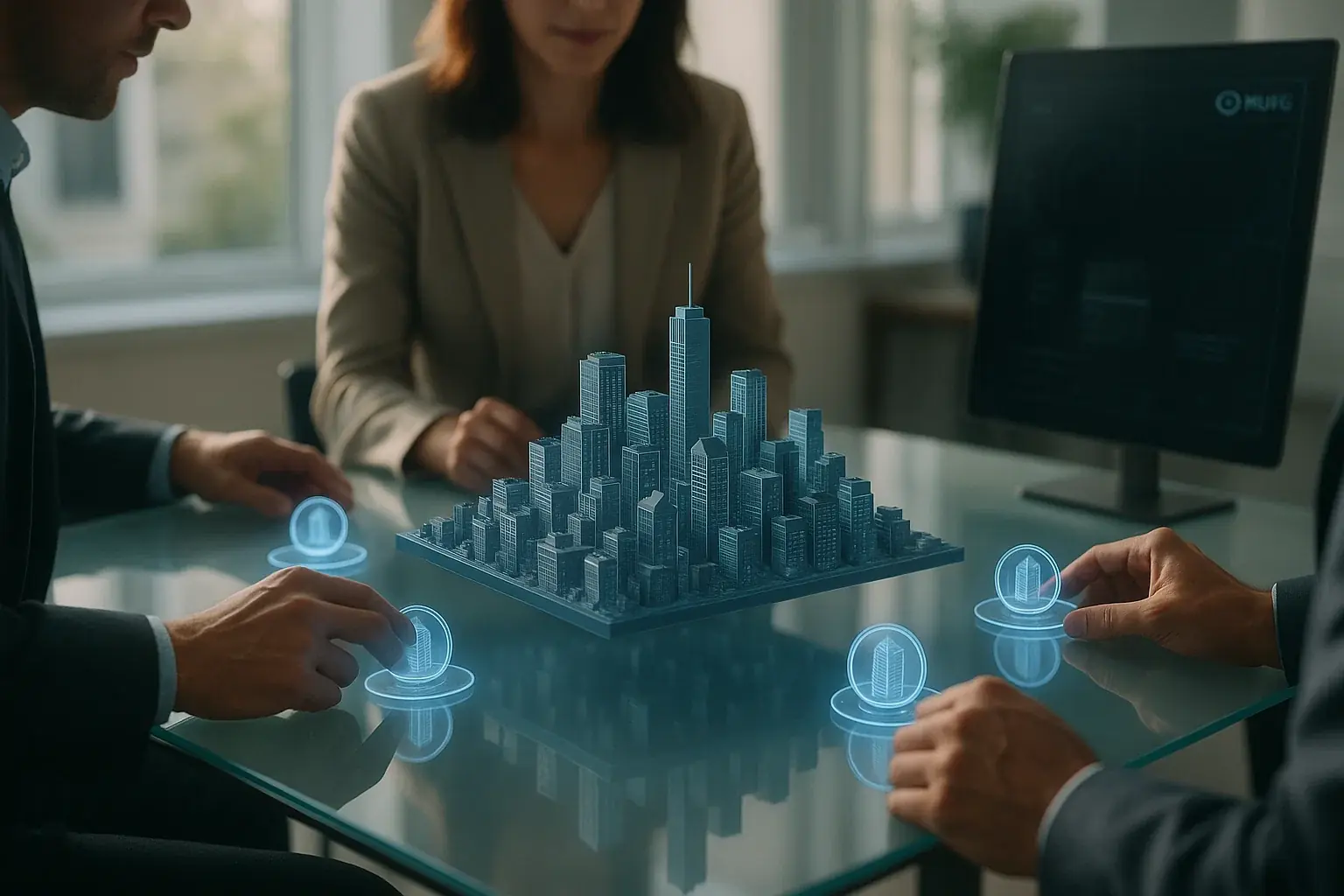三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、個人投資家に特化したセキュリティトークンプラットフォーム「ASTOMO(アストモ)」を立ち上げ、デジタル資産分野への重要な一歩を踏み出しました。
ASTOMOは個人投資家にとって画期的なもので、わずか653ドル(10万円)の初期資金で分有不動産に投資することができます。
これにより、従来は機関投資家や富裕層向けの商品であった区分所有への参入の敷居が劇的に低くなりました。
日本のトークン市場の拡大
MUFGの参入は、他の日本の大手金融機関の動向に従っている。日本のセキュリティー・トークン市場は過去2年間、急速に拡大しており、日本の厳格な金融商品取引法の下で発行が集中している。
業界の予測では、市場はさらに拡大し、累計発行額は22億9000万ドル(約3500億円)に達する可能性があるとされているが、正式なスケジュールは示されていない。
他の金融大手もこの成長に貢献している。2025年2月、大和証券はトヨタグループの企業向けに650万ドル(10億円)のトークン化社債を発行したが、発売後すぐに完売した。
同様に、2023年後半以降、みずほ信託銀行と野村ホールディングスはセキュリティトークンを発行しており、主に不動産受益証券を担保としている。
セキュリティトークンは法的に「電子的に登録された譲渡可能な権利」と定義され、投資家保護やマネーロンダリング防止基準など、従来の金融商品と同様の規制順守要件が適用されます。
厳しい規制と将来の展望
日本の厳しい規制の枠組みは、際立った特徴です。トークン化された資産が分散型金融プロトコルに統合されている他の法域とは異なり、日本ではほぼすべての発行が認可された金融機関を通じて行われます。
歴史的な流動性の制約に対処するため、大阪デジタル取引所(ODX)は2023年12月にセキュリティトークンの二次取引プラットフォームを立ち上げました。
さらに、二重課税の問題を解決し、トークン化の対象となる資産を拡大する可能性のある税制改革が進行中で、動産資産やベンチャーキャピタルファンドの持分も含まれる可能性があります。
規制モデルは伝統的な金融とデジタル資産の中間に位置しますが、市場の長期的な成功は、継続的な商品の多様化、流通市場の流動性、国境を越えた投資の流れを制限する国際的な規制の分断の解消にかかっています。
MUFGは新しいASTOMOプラットフォームについて、具体的なユーザー獲得目標や収益予測の提示を避けた。